こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ 〜不登校とともに流れる、のんびり時間〜」にお越しくださり、ありがとうございます。
子どもが不登校になったとき。
その苦しさって、経験した人にしか分からないものがありますよね。
「この子だけ、みんなと違ってしまった」
「勉強、大丈夫かな」
「将来、このままで社会に出られるの?」
「普通じゃないって、どういうこと?」
「私の育て方、間違ってたのかな…」
そんな風に思っては、自分を責めてしまう。
心が重たくて、張り裂けそうで、夜になると静かに泣いてしまう。
SNSを見ていると、そんな思いを抱えたママたちが本当にたくさんいます。
でも私は今、学校に行けなくなった我が子を見ても、以前ほど辛くありません。
今日は、どうしてそう思えるようになったのか、お話ししたいと思います。
「学校に合わない子はいる」って思ってた
うちの子はもともと、学校にあまり馴染めないタイプでした。
ただ、私はそれを「悪いこと」とは思っていませんでした。
なぜなら、私自身が子どもの頃、
「なんだか学校って居心地悪いなあ」と感じながら過ごしていたから。
馴染めない子は一定数いるんだって、自分の経験から思っていたんです。
だから、「なんとか馴染ませなきゃ」とも、「このままじゃダメ」とも思わなかった。
「そういう子もいるよね」くらいの、ちょっと肩の力が抜けた感じで見ていました。
そして、ついに「学校へ行けない」という状態になったときも、
「うん、やっぱり相当合わなかったんだな」と、割と冷静でした。
それが私の子育てのせいとは、正直あまり思いませんでした。
「人と違っても大丈夫」と知っていた
私は過去に、メンタルの不調を経験したことがあります。
だからこそ、どんなにしんどい時期があっても、
ちゃんと回復するタイミングがやってくることを知っています。
それと同じように、
「普通じゃない道を歩いても、ちゃんと生きていける」
「みんなと違っても、大丈夫」
という感覚が、私の中にはあるんです。
勉強の遅れについても、不登校支援の本や先輩ママたちの言葉から、
「子ども自身がその気になれば、いくらでも取り戻せる」と知って安心できました。
実際、今社会で活躍している人の中にも、
不登校を経験してきた方がたくさんいると知ってからは、
「この子もきっと大丈夫」と思えるようになりました。
「この子は私と違う人間」と意識してる
そして、たぶん何より大きいのは、
「この子は私とは違う人間なんだ」と、ちゃんと意識していること。
私は、母の期待を一身に背負って育った子どもでした。
だからこそ、その重さや息苦しさを、痛いほど知っています。
我が子には、そんな重荷を背負わせたくない。
「この子はこの子の感じ方で生きていい」
「自分で選ぶ人生を、私は応援するだけ」
そうやって、信じることにしています。
わが子の「成長力」を信じることにした
心と体の疲れが少しずつ癒えてきた最近は、
親子でたくさん話すようになりました。
すると、まだ10歳の小さな心と頭で、
彼なりに一生懸命、色んなことを考えているのが伝わってきます。
学校のこと、フリースクールのこと、将来のこと…。
迷いながらも、試行錯誤しながら、ちゃんと自分なりの答えを探している。
その姿を見たとき、私は思いました。
「今、この子は“自分の力で”乗り越えようとしてる」
「その力を、親の私が信じてあげなくてどうする?」
不登校って、「学校に行けなくなること」だけが本質ではないのかもしれません。
その子にとって必要な、ものすごく大きな成長のプロセスなのかもしれません。
よく、急に背が伸びるときは「骨が痛い」って言いますよね。
あれと同じことが、心の中でも起こっているのかもしれない。
だとしたら、その「痛み」は悪いものではなく、
むしろ「成長の証」なのかもしれません。
おわりに:頑張りすぎないで、抱え込みすぎないで
優しいママほど、
「この子の痛みを、何とかしてあげたい」って一生懸命になります。
その気持ちは、本当に素晴らしいこと。
でも、頑張りすぎて、子どもの痛みまで自分で背負い込んでしまうと、
ママ自身が壊れてしまいます。
だから、どうか覚えていてください。
わが子が学校に行けないのは、あなたの責任ではありません。
それは、その子と環境との相性だったり、
その子が今いる場所で、自分のペースで育とうとしているサインだったりする。
そして、「不登校」は“終わり”じゃなく、きっと“始まり”です。
少しだけ視点を変えることで、
「この子、今すごく大切なことを学んでるのかもしれない」
そう思えるようになったら、ママの心も少し軽くなるかもしれません。
そんなママがひとりでも増えたらいいなと、私は願っています。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
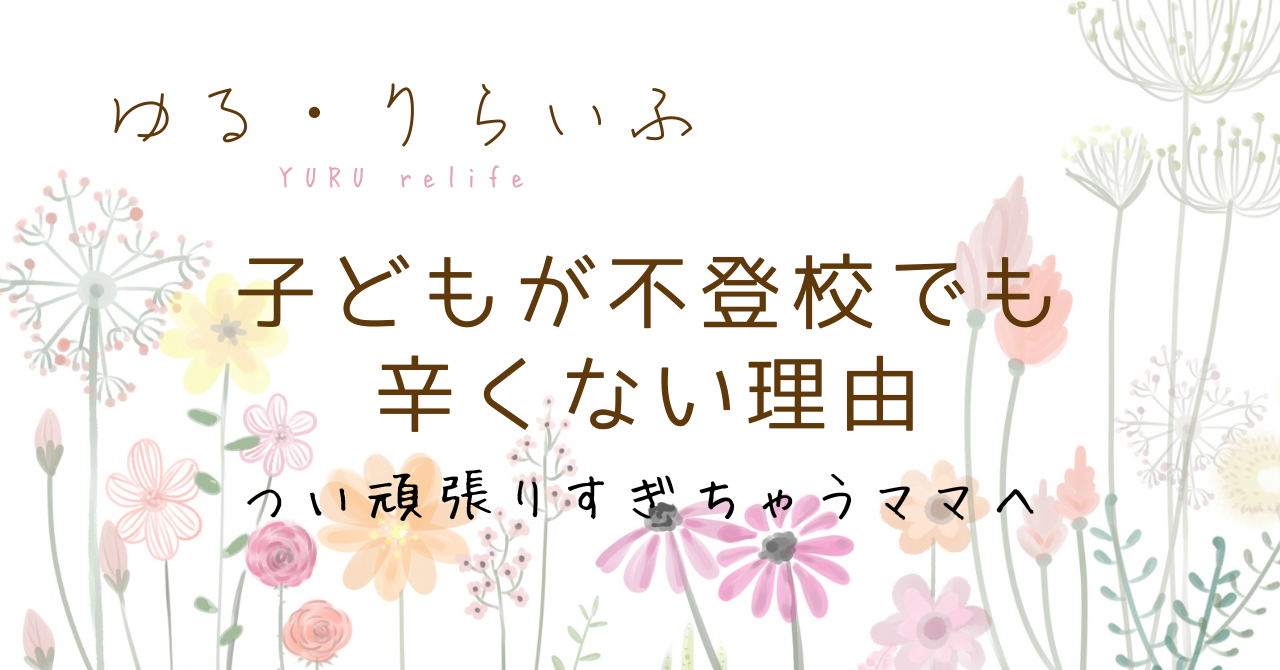
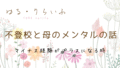
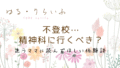
コメント