こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ 〜不登校とともに流れる、のんびり時間〜」にお越しくださり、ありがとうございます。
「このままずっと学校に行けなかったら、どうなるんだろう」
「行けないままの生活って、どうやって過ごすの?」
我が家の息子は、今は学校に通っていません。
でも今は、元気に、笑顔で、過ごしています。
今日は、我が家のリアルな記録をお伝えします。
「学校に行けない」その不安が、少しでも軽くなりますように。
不登校の日々って、どんなものなの?
不登校になってから回復するまでの期間は、本当に人それぞれ。
半年で学校に戻る子もいれば、数年かかる子も。
でも、期間の長短に関わらず「学校に行かない日々は、どんなふうに過ごしているのか?」は、気になるところだと思います。
今回は、我が家がどんなふうに暮らしているかをありのままに書いていきます。
不登校にならなかったけど…
最初のサインは、小学1年生の頃でした。
こちらの記事で詳しく書いていますが、今思えば不登校につながるサインがいくつも出ていました。
特に息子は学童に強い拒否反応を示していました。
ですが民間学童を併用するようになって、「家庭・学校以外の居場所」ができたことで、少し安定しました。
それで月に2日は必ず休みながらも、なんとか登校を続けていたのです。
今思えばこの時もっと重く受け止めて、環境の調整をしてあげていたら、その後の不登校は防げたのかもしれません
この時の学び
- 「あれ?」と思ったら、迷わず動く
- 今の環境が合わないなら、合う環境に「調整」してあげていい
- 本人が“自分らしく”過ごせる場所があると気持ちは安定する
- 親の勘って、実はけっこう当たる。信じていい
環境が変わり、一気に噴出
高学年になって転校をしたのですが、これが大きな転機に。
「新しい環境が苦手」「予測できない変化が苦手」という特性の強い息子には、相当なストレスだったようです。
さらに、新しいクラスは学級崩壊気味で、先生は学級運営にお手上げ状態…。
唯一の心の支えだった民間学童からも離れたため、ストレスが一気に体と心に出始めました。
- 頭痛・腹痛
- 耳が聞こえない、目が見えない
- 赤ちゃん返り、癇癪
- 自己肯定感の低下
私自身、過去に適応障害で会社に行けなくなった経験があるので、「これはまずい」とすぐに察知。
本人は「行かなきゃ」と思っていたけれど、児童精神科の先生と相談して、しばらく学校を休むことを決断しました。
休むと決めた後、どんな毎日を送ったのか
児童精神科の先生には「目指すゴールを明確にしよう」と言われました。
私が出した答えは、
「学校に行っても行かなくてもいい、この子が笑顔で元気に生きてくれること」
それを受けて先生からのアドバイスは以下の通りでした
- 無理な登校はNG
- 勉強をしたい気持ちがあるので、塾や適応教室など勉強が続けられる環境整備を
- フリースクールや放課後デイサービスなど、「第3の居場所」を持つ
先生のアドバイスをもとに、学校に行かない日々の過ごし方を模索し、次のような生活に落ち着きました。
我が家の日常
- 朝は下の子(元気に登校中)と一緒に起きる
- 最初は日中ほとんど寝ていた(寝かせておいた)
- 14時まではゲームやYouTubeはNG(でも最初はその元気もありませんでしたが)
- 塾の宿題やドリルを少しだけ(本人の勉強に遅れる不安の解消のため。無理強いはしない)
- 毎日一回は買い物などで外に出る(私の買い物や用事のついでに一緒に出かけました)
- 習い事と塾はそのまま継続(本人にとって居場所となっているため)
振り返れば、特別なことは何もしていません。
ただ、学校に行っているときと大きく変えないように、また生活リズムだけは崩さないようにしていました。
この時の学び
- 腫れ物のように扱わない、いつも通りに接する
- でもそっとしておく(自分から話したくなるまで、動きたくなるまで待つ)
- 「早寝早起き、日光を浴びて散歩、ちゃんとご飯を食べる。」結局メンタル低下に一番効くのはこの3つ
- 「学校」の話題は、本人が言い出すまでは出さない
笑顔が戻ってきた頃に、次の一歩を
2ヶ月ほど経って、息子の笑顔が少しずつ戻ってきました。
それをきっかけに、フリースクールの見学へ。
現在は週に数日、通っています。
そこからますます元気を取り戻し、今では学校に行っていないとは思えないほどです。
まるで“普通の小学生”のようです。
ただし、学校に戻ることにはまだ抵抗感が強いようなので、夏休みに今後のことを親子で話し合う予定です。
ここでの学び
- 居場所は「家庭」「学校」だけじゃなく複数あった方がいい
- 親は「守る」だけでなく、時期が来たら「次に進む手助け」もする必要あり
- 子どもは、子どもなりにちゃんと考えているので、本人の意見は尊重する
- 思春期に入る頃は「学校に戻すこと」よりも「社会で生きていく準備」に視点を
おわりに:必要なのは「今、できること」
不登校がいつ終わるかなんて、誰にもわかりません。
でも、「このまま不登校になったら、この子の人生、お先真っ暗になるのかも?」と思わなくて大丈夫。
「この子にとって何が大切か?」を軸に考え、毎日を丁寧に暮らしていけば、必ず光が見えてくるのだと、この経験から感じています。
我が家も、まだ道半ば。
それでもひとつ言えるのは、学校に行かなくても、笑って、希望を持って生きていけるよってこと。
先の見えない道ではありますが、きっとこの先には素晴らしい景色が見えるはずと信じて、一緒に歩いていきましょう。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
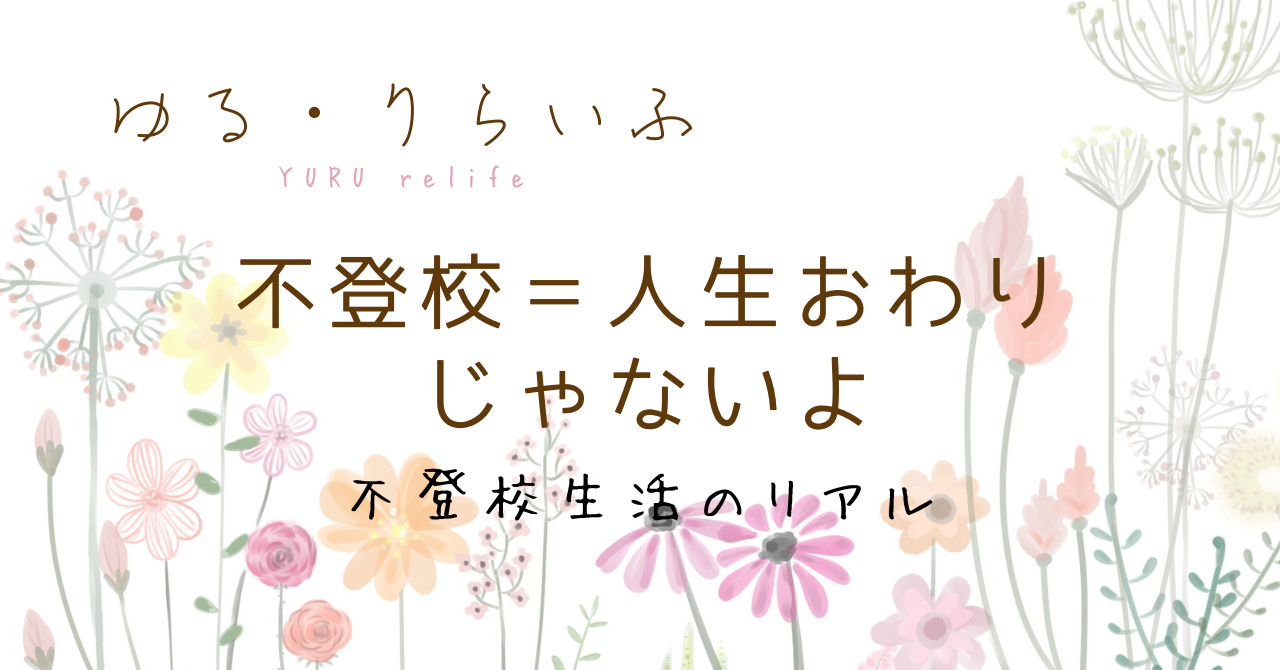
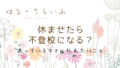
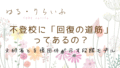
コメント