こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ ~不登校とともに流れる、のんびり時間~」にお越しくださり、ありがとうございます。
「学校に行きたくない」──子どもがそう言い出したとき、親としてどう対応するかは、本当に悩ましい問題です。
行かせるべきなのか、それとも休ませた方がいいのか…。
正解が見えないからこそ、判断に迷い、時に自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
私自身も、その決断を迫られた母親のひとりです。
今回は、「休ませる決断」をした私の経験をもとに、同じように悩んでいる方へのヒントになればと願って綴ります。
まるで適応障害の会社員のようだった
我が子が「学校に行きたくない」と言い出したとき、私はすぐには休ませる決断ができませんでした。
子ども自身も、「行きたくない」と言いながら、頭では「行かなくては」「行くべき」と思っているようで、「それなら行かせた方がいいのでは?」と、私も揺れ動きました。
それでも、朝になると腹痛や頭痛が現れ、玄関先で涙を流す姿を見ていて、思い浮かんだのが「適応障害で苦しむ会社員」の姿です。
職場に行こうとすると体が動かない。無理をすれば表面上はなんとかこなせても、心がボロボロになってしまう…。
そんな姿と、目の前の我が子が重なったのです。
「休ませるべきか」の判断に正解はない
「こんなときは休ませましょう」と言える明確な指針があれば、親としてはどれほど楽かと思います。
ですが、不登校の難しさは、「状況を一般化できない」ところにあります。
同じ「行きたくない」という言葉でも、その背景や子どもの心の状態は一人ひとり違うんですよね。
だからこそ、「休ませる」か「行かせる」かの判断には、親の観察力と直感がとても重要になると感じています。
私が「休ませよう」と決断した理由
私の場合、学校に行きたくないという子どもの言葉の背景に、相当な精神的な疲弊があると感じました。
ある専門家が話していたことが、私の背中を押してくれました。
「子どもが学校に行きたくないと言い出すのは、心が追い込まれている証拠。
それは“問題の始まり”ではなく、“子どもなりに考え抜いた末の最終手段”です」
この言葉を知っていたからこそ、私は「これ以上、心を追い詰めてはいけない」と判断しました。
それで、「今は休もう」と伝えることにしたのです。
フリースクールへの拒否反応は「拒否の質」が違った
それからしばらくして、フリースクールに通うことになりましたが、この時も最初は強い拒否反応がありました。
でも、その「行きたくない」は、学校のときとは違う感触がありました。
「行くべきと頭ではわかっているけど、怖い」「知らない人ばかりで不安」
そんなふうに、未知の環境に対する一時的な拒否に感じられたのです。
学校のときのような“心が壊れてしまいそうな感覚”とは違いました。
だから、こちらは「少し頑張って行ってみようか」と促してみる価値があると感じ、ゆっくりと進めていくことにしました。
一番大切なのは「その子自身をしっかり見ること」
学校に行かせるか、休ませるか──この判断に、正解はありません。
でも、親がその子を長年見てきた経験から得た“感覚”は、確かなものだと思っています。
- 今日は顔色が違う
- 言葉には出していないけど、すごく無理してる
- 逆にこれは一時的な不安かも
そういう、言語化しづらい「勘」こそ、私たち親が大切にしていい部分だと思うのです。
正解がなくても、「我が家なりの答え」は見つけられる
不登校の対応にはマニュアルがありません。
けれど、だからこそ、「この子とこの家庭に合ったやり方」を丁寧に見つけていくしかないのだと思います。
私もまだ迷うことは多いです。
でも、「あのとき、無理に行かせず休ませたことは間違っていなかった」と思っています。
そしてこれからも、その都度、その時の子どもを見ながら、小さな判断を重ねていきたいと思っています。
おわりに:迷っていい、でも「信じて、決めてみる」
「どちらが正しいの?」と迷ってしまうこと、何度もあると思います。
でも、迷うということは、それだけ子どものことを真剣に考えている証。
だからこそ、「自分の判断を信じて、決断してみる」。
それも、子どもとの関わりを続けていくうえで、とても大切な姿勢だと私は感じています。
あなたの勘は、きっと間違っていないと思います。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
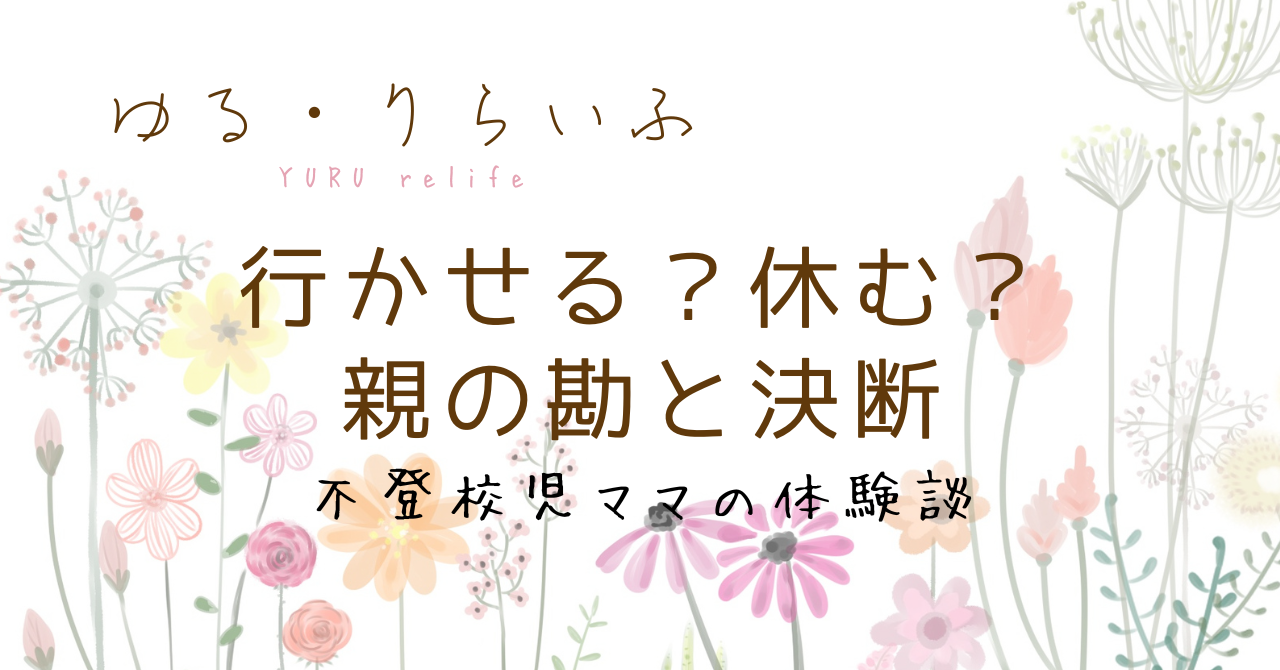
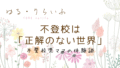
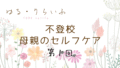
コメント