こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ 〜不登校とともに流れる、のんびり時間〜」にお越しくださり、ありがとうございます。
夏休みが終わり、2学期が始まるタイミング。
長期休み明けに学校に行けない子どもって、意外と多いんです。
行き渋りや不登校の子を持つママは、心がザワザワしちゃう時期かもしれません。
今日は、そんなママたちの心が少しでも軽くなるヒントをお届けします。
夏休み明けの不安――学校へ行けない子どもと親の心
「2学期からは学校に行く!」と宣言した我が子。
でも始業式の日、玄関から出られない…。
思わず「なんで?」とイラッとしたり、モヤモヤしたりするのは自然なこと。
なぜなら、親の「学校に行ってほしい」という期待が裏切られたことからくる感情だから。
「学校に行けば安心」「学校に行けば人並みに大人になれる」
そう思う気持ちは、親なら誰でも持ってしまうものです。
だから学校に行かない選択は、「この子、大丈夫かな…」という不安を自然に引き起こします。
でも、こうした気持ちは日本で育った私たちにとってごく自然なこと。
子どもが学校に行けないことで落ち込む自分を責めなくて大丈夫なんですよ。
私の体験からわかったこと
私も以前、メンタル不調で数年、社会から離れたことがあります。
働きたいのに体が言うことをきかず、会社にも行けない…。
最初は本当に不安でいっぱいでしたが、今は社会復帰して普通に働けています。
メンタルの回復は年単位でゆっくりですが、必ず良くなる。
自分の経験からそう感じています。
そして同時に思うのは、子どもの不登校も必ず「終わり」があるのだろうということ。
学校に行けない今だけで、将来を決めつける必要はないんだと思っています。
学校に行けなくても、この先の人生が詰むなんてことはないと、私は思っています。
不登校経験者のその後――将来は意外と安心
文部科学省の調査(2003年)によると、不登校を経験した人の約8割が20〜30代で就労や進学など社会参加を果たしているそうです。
支援が十分でなかった時代でも、多くの人が成人後に社会で活躍しているんですね。
実際、小中学校時代に不登校だった子どもが、10代後半くらいから自ら動き出すケースも多く見られます。
子どもは成長の途中。体だけでなく心や思考も少しずつ育ち、社会と折り合いをつける力を身につけていきます。
今は学校に行けなくても、その成長を信じて見守ることはできると感じています。
令和型子育ては「しなやかさ」が鍵
昭和・平成の時代は、我慢や忍耐が美徳とされてきました。
でも令和の子どもたちは、自分の個性を大切に育ち、違いや多様性を自然に受け入れています。
だから親も、子どもの状況や個性に合わせて柔軟に対応することが大切かもしれません。
気合や根性で乗り越えるより、しなやかに寄り添う方が、親子にとってきっと自然で、そして安心できるような気がするんです。
まとめ――親も子どもも、自分の感じていることを大事に
子どもの不登校で心がザワザワするのは自然なこと。
自分の気持ちを責める必要はありません。
でも同時に、子どもの「行きたくない・行けない」という気持ちも大切に受け止めることが大事です。
親の心に寄り添い、子どもの気持ちにも寄り添うことで、不登校はそんなに辛いものではなくなると思っています。
どうかご自分にも、お子さんにも、優しくしてあげて下さいね。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
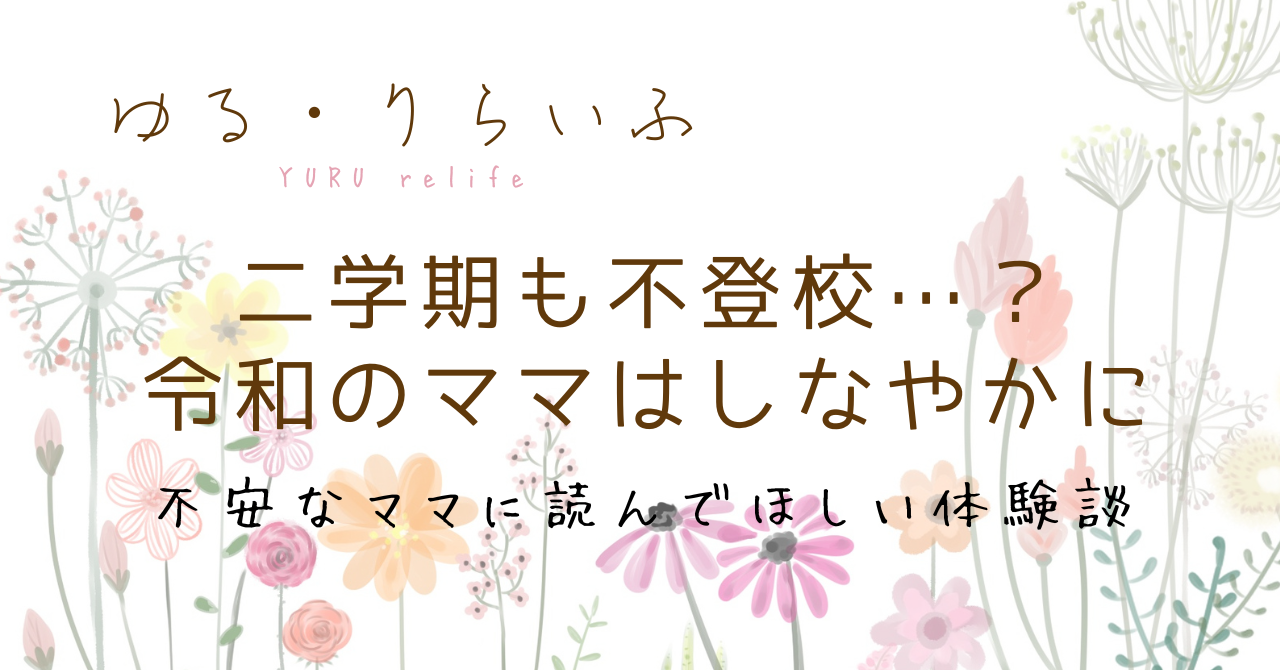
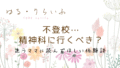
コメント