こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ 〜不登校とともに流れる、のんびり時間〜」にお越しくださり、ありがとうございます。
先日、同じように不登校のお子さんを育てているお母さんとお話しする機会がありました。その中で私自身が感じたことを、書き留めておこうと思います。
◼️不登校の子どもを育てるママ同士、だからこそ共感できたこと
今回お話ししたのは、違う地域に住むお母さん。お子さんが学校に行けていない、という点では同じ状況でしたが、学校や行政の対応は思いの外異なっていました。
「不登校」とひとことで言っても、置かれている環境やサポート体制は本当に人それぞれなんですね。改めてそれを実感しました。
でも、それ以上に強く感じたのは——
「わかる」「私も同じ気持ちだった」という“共感”の力でした。
日々の小さな悩み。子どもへの接し方。周囲の人との距離感。学校とのやり取り……。
細かな違いはあっても、母親としての戸惑いや迷いには、共通点が多かったんです。
気づけば、思っていた以上に長い時間を一緒に話していました。話し終わった後は、なんだか心がふわっと軽くなっていました。
◼️「正解がない」からこそ、支える側の心のケアが必要
不登校の子どもを支える毎日は、想像以上にエネルギーが必要です。
学校との連絡や調整、家庭内でのサポート、兄弟姉妹との関係……。
どうしても、母親が一人で背負いがちな現実があります。
「どうすればこの子にとって一番良いんだろう?」
「これでいいのかな? 間違っていないかな?」
正解のない問いに向き合いながら、必死に考え、動いている。でもその一方で、自分自身を責めてしまったり、誰にも言えずに落ち込んだり、泣いたり……。
そんな風に、心がギリギリの状態になってしまうこと、きっと多くの方が経験しているのではないでしょうか。
◼️ただ話すだけ。それだけで救われることがある
今回のお話を通して、改めて感じたのは「ただ話すだけって、本当に大切」だということです。
何かアドバイスがほしかったわけでも、答えが知りたかったわけでもありません。
ただ「そうだよね」「私もそうだったよ」と、うなずいてもらえることが、こんなにも安心感につながるんだと実感しました。
同じ立場で話ができる相手がいるだけで、「自分だけじゃないんだ」と思える。
「一緒に歩いている人がいる」と感じられる。
それが、日々プレッシャーの中でがんばっている母親の心を、そっと支えてくれる力になるのだと思います。
◼️不登校の親の会や当事者同士のつながりを持ってほしい
もし今、不登校の子を育てながら、ひとりでがんばっているお母さんがいたら——
ぜひ、「不登校の親の会」や「当事者会」など、同じ境遇の人たちとつながる機会を探してほしいです。
自分の気持ちを、少しでも話せる場所があるだけで、驚くほど気持ちがラクになることがあります。
話すことで、自分を客観的に見られたり、気づきを得られたり、何より「共にがんばっている人がいる」と感じるだけで、心の安定に繋がります。
私自身、このブログや音声配信を通して、そんな“つながり”を少しずつ作っていけたらと願っています。
どうか、ひとりで抱え込まず、安心できる場所を見つけてくださいね。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
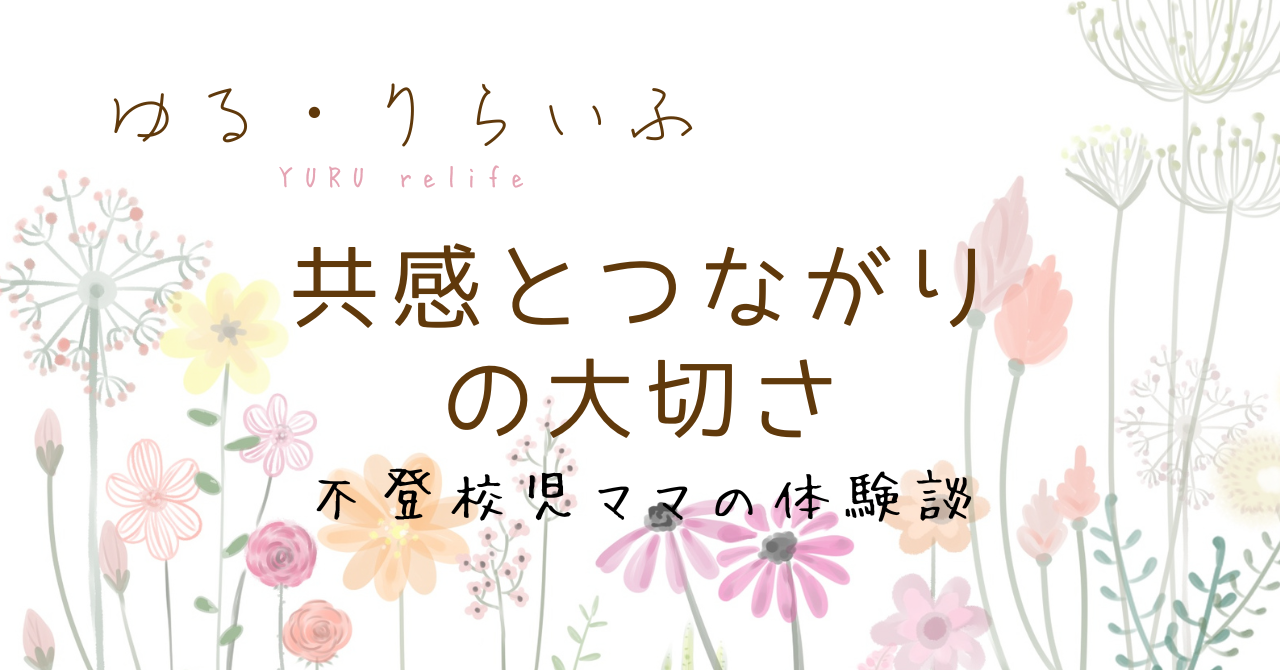
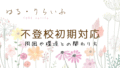
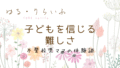
コメント