こんにちは、まいこです。
ブログ「ゆる・りらいふ 〜不登校とともに流れる、のんびり時間〜」にお越しいただきありがとうございます。
このシリーズでは「フリースクールを選ぶまで〜息子と見つけた“新しい居場所”」と題して、小学生の息子が学校に行けなくなった時のこと、そして私たち親子がどんなふうに乗り越えていったのかを、数回に分けてお話していきたいと思います。
第1回の今回は、「学校に行けない…。私たち親子はどうしたのか」についてお届けします。
不登校は突然に、ではなく「少しずつ」始まっていた
わが家の息子が初めて登校しぶりを見せたのは、小学校に入学してすぐのことでした。
学校の様子を聞いても全く話さない。帰宅すると毎日ソファに倒れ込んでじっと動かない。学校に行くことをしぶり、学童は何度もお休みして、その都度私は仕事を休んだり早退したり。
でもその頃の私は、「新しい環境に慣れていないだけ」とどこかで軽く考えていたんです。ちょうどその時期は私自身も仕事と育児の両立に疲れ切っていて、毎日をなんとかこなすのが精いっぱいでした。
「ちゃんと向き合ってあげられなかったな…」
今振り返ると、そんなふうに思うこともあります。
4年生の転校後、心と体に現れたサイン
私が育児に専念するために一度仕事をお休みした後、少しずつ家庭の空気にもゆとりが戻ってきました。けれど、息子は月に1度は何らかの理由でお休みする状態が続いていました。
それでも、「この子はもともと体が丈夫じゃないからなぁ」と、その時も私はあまり深く考えることなく過ごしていました。
しかし4年生で転校したのをきっかけに、「学校に行きたくない」と言うようになり、朝になると頭痛や腹痛を訴える日が増えてきました。
最初は「転校の一時的なストレスだろう」「きっとすぐ慣れる」と思っていたのですが、だんだんと「僕なんていない方がいい」「消えてしまいたい」といった言葉が息子の口から出るようになってきて…。
いじめや教師とのトラブルはなかったはず。でも、学校という場所が、息子にとっては心の負担になっていたのかもしれません。
「今、大切なのはこの子の心を守ること」
私はあるとき、ふとこう思いました。
「今の学校は、息子にとって安心できる場所じゃないのかもしれない」
「そんな場所に、無理をしてまで通わせる必要ってあるのかな?」
このまま無理に学校に行かせることが、息子の自己肯定感をさらに下げてしまうのでは?と感じた私は、まず児童精神科を受診しました。その時に、自閉スペクトラムの疑い、と言われたのです。
定型発達の子供達に合わせて運営されている学校環境は、彼にとっては努力が必要な場面が多い、だから辛くなってしまうのだろうということでした。そこで主治医の先生とも相談し、心のSOSが出ている日はしっかりと休ませるようにしました。
でも、「学校に行けない自分」を受け入れるのは、想像以上に息子にとってつらいことだったようです。
「安心できる居場所って何だろう?」と考えはじめた私たち
そこから、私たち親子は「じゃあどうすればいいんだろう?」と一緒に考える日々が始まりました。
次回は、そんな私たちがどのように“新しい居場所”を探し始めたのか、「安心できる場所って何?」というテーマでお話ししたいと思います。
不登校という選択肢を前向きにとらえるヒントや、フリースクールとの出会いまでの過程を、少しずつ綴っていきますので、よければまた覗いてみてくださいね。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
不登校の子どもを育てる同じ立場の方に、少しでも届きますように。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
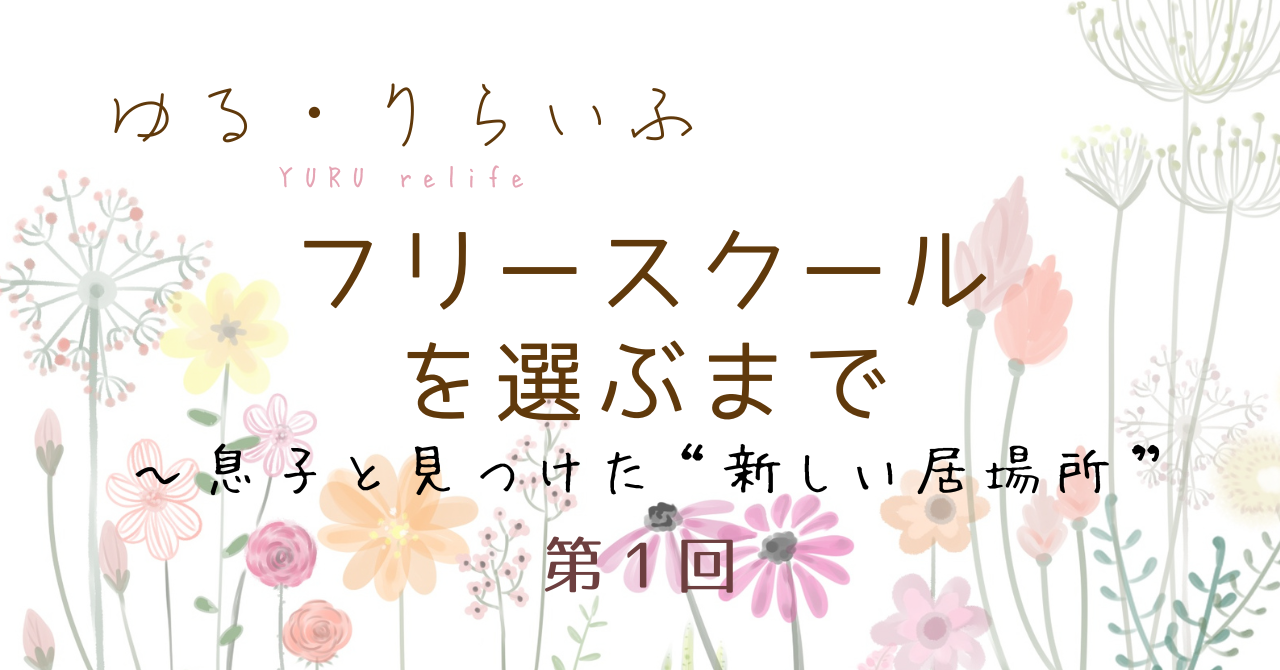
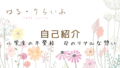
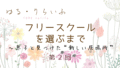
コメント