こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ ~不登校とともに流れる、のんびり時間~」にお越しくださり、ありがとうございます。
子どもが学校に行けなくなったとき…
いちばん動揺しているのは、もしかしたら親の私たちかもしれません。
「なぜ?」「どうすればいいの?」
そんな不安や混乱の中で、親としてどうあるべきか…
私自身、何度も立ち止まりながらも歩き続けています。
今回は「親自身の心構え編」として、不登校初期に親が大切にしたい5つの視点をご紹介します。
同じように悩むお父さん・お母さんに、少しでも寄り添えたらうれしいです。
原因究明にこだわりすぎない
「どうして学校に行けなくなったのか?」
その理由が知りたくて、親としてあれこれ考えがちですよね。
でも、不登校の“本当の理由”って、実は子ども自身もまだ分かっていないことが多いそうです。
数年たってから初めて言葉にできる……そんなこともよくあります。
それなのに、親が「原因探し」にこだわりすぎると、かえって子どもを追い詰めてしまうことも。
「親として何か間違えた?」と自分を責めても、前には進めません。
まずは原因よりも、「今のわが子の心をどう安定させるか」に目を向けた方がいいかもしれません。
「人と違う道を行く」覚悟を決める
日本では、「みんなと同じ」が安心の基準。
だからこそ、わが子が不登校になると、「うちだけが違う」と焦ったり、周囲の目が気になったりしますよね。
でも、今は“子育ての正念場”かもしれません。
周りの目よりも大切なのは、目の前にいるわが子。
人と違う道を選ぶことは、決して“間違い”ではありません。
むしろ親が「その道もありだよ」と腹をくくって受け止めることで、子どもは安心して歩み出せるもの。
他の家庭と比べて落ち込む日もありますが、そんな時は「わが子のペースを大事に」と心の中で何度もつぶやいてみてください。
一人で抱え込まない
「不登校って、なんだか人に言いづらい」
そう思う方も多いと思います。私もそう感じていました。
でも今思うのは——
不登校は、隠すことでも、恥ずかしいことでもありません。
そして、助けを求めることは“弱さ”ではなく“強さ”です。
話を聞いてくれる人、共感してくれる人、力になってくれる支援機関はたくさんあります。
ただ、こちらから声を上げないと気づいてもらえないだけ。
愚痴でも、悩みでも、専門機関への相談でもOK。
自分を支えてくれる“つながり”を持つことで、気持ちはぐっと楽になりますよ。
親が安定することを最優先に
不登校の子どもは、実は親のちょっとした不安や焦りにとても敏感です。
だからこそ、まずは親自身の心と体を安定させることがとても大切。
でも……そうは言っても、不安になるのが親心ですよね。
そんなときは、正しい情報を知ること。
不登校の仕組みや対応法を学ぶことで、少しずつ不安が和らいでいきます。
そして、どんなに悩んでいても「しっかり食べて、ちゃんと寝る」こと。
睡眠不足や体調不良は、心の余裕を確実に奪っていきます。
まずは、自分自身を労わってください。
親の笑顔は、子どもにとって大きな安心になるはずです。
「焦らない」と自分に言い聞かせる
不登校は、短距離走ではなく長距離マラソン。
回復には年単位の時間がかかることも珍しくありません。
学校に行けなくなるまでに、子どもがどれだけ無理をしてきたか。
それを癒すには、それ以上の時間が必要だと私は感じました。
焦らない。比べない。
「今はその時期じゃない」と、自分にも言い聞かせて。
先が見えない中でも、“わが子の今”を大切にする気持ちを持ち続けたいですね。
おわりに:親も「自分を責めない」ことが大切です
子どもの不登校を経験すると、「自分の育て方が悪かったのかな」と思ってしまいがち。
でも、本当に大切なのは「これからどうするか」です。
今はしんどくても、親としてできることは必ずあります。
そして、親もまた、ひとりの人間。
無理せず、自分をいたわりながら、子どもと一緒に一歩ずつ歩んでいきましょう。
次回は「3. 周囲・環境への対応編」として、学校や地域、家族との関わりについてお届けする予定です。
同じように悩む方へ届くよう、この記事がよければシェアしていただけるとうれしいです。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
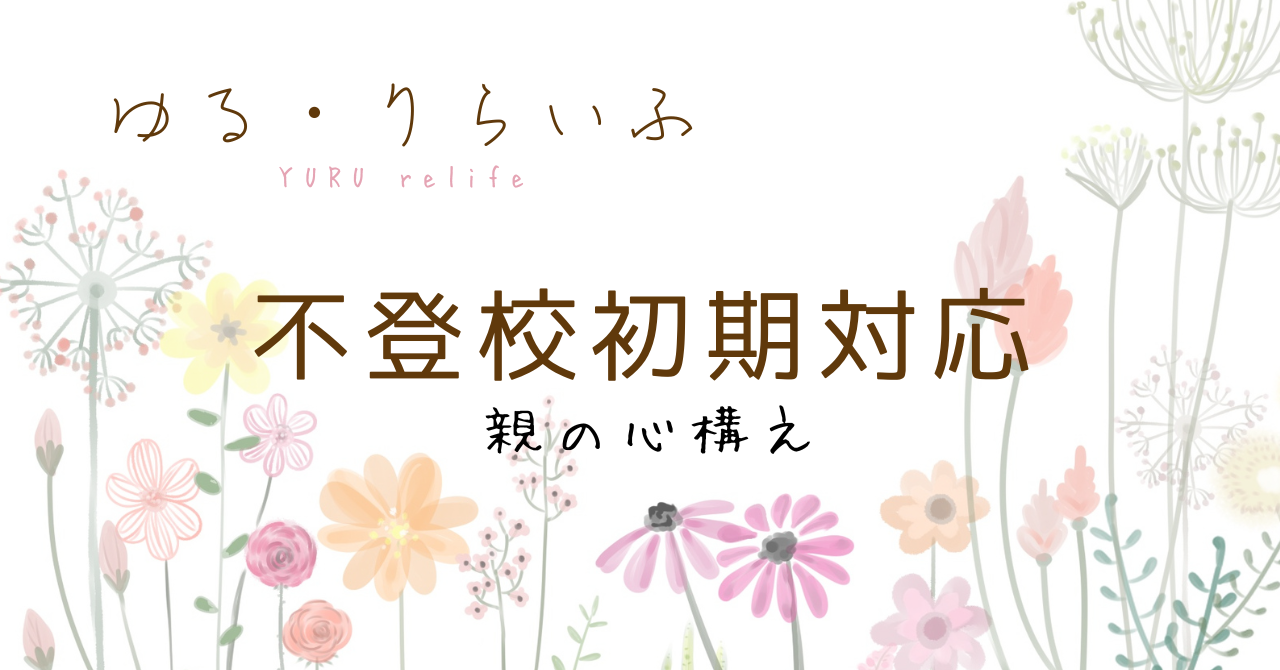
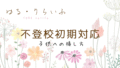
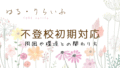
コメント