こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ ~不登校とともに流れる、のんびり時間~」にお越しくださり、ありがとうございます。
「明日は学校、行けそう?」
その一言が、子どもにとって大きなプレッシャーになることがあるそうです……。
わが子が「学校に行きたくない」と言い出したら、親としてはどう対応すればいいのか、不安や戸惑いが押し寄せてきますよね。
今回は、不登校の初期において、子どもへの接し方として大切にしたい5つの視点をまとめました。
どれも私自身が実際に体験し、悩み迷いつつ学んできたことです。
同じように不登校のお子さんを抱える方の参考になればうれしいです。
「登校刺激」を避ける
不登校の初期に大切なのは、「登校刺激」を控えること。
登校刺激とは、「学校には行かなくていいの?」や「そろそろ行けそう?」といった、学校へ行くことを促すような言葉や態度のことです。
もちろん、最終的には社会との接点を持てるようになるのが理想。
ですが、不登校になったばかりの子どもは、心が疲れ果てている状態です。
まずは、心の“安全基地”をつくることを優先しましょう。
無理に登校を促すのではなく、安心できる環境づくりが大切です。
家庭内の安心・安全を最優先する
子どもが学校に行けない理由はさまざまですが、共通して言えるのは「学校が安心できる場所ではなくなってしまった」ということ。
1ともつながりますが、子どもにとって心から安心できる場所が必要です。
特別なことをする必要はありません。
一緒に食事をする、声をかける、そっと見守る……
それだけでも、子どもにとっては「家にいていいんだ」と感じられるはずです。
“学び”へのこだわりを一度手放す
学校に行けないとなると、「勉強が遅れてしまうのでは」と不安になりますよね。
でも実は、子ども自身もその不安を感じていたりします。
親が不安に引きずられてしまうと、子どももますますプレッシャーを感じ、心の負担が増してしまうことも。
今は“学力”より“心のケア”を最優先に。
多くの不登校支援者や当事者が口をそろえて言うのは、「学び直しはあとからでも十分間に合う」ということです。
子どもを信じて、まずはしっかりと休める環境を整えましょう。
“休むこと”を肯定的に伝える
学校に行けなくなったわが子を見て、私は「会社に行けなくなった大人」と重なる部分があると感じました。
心が限界を迎えて、エネルギーが枯渇した状態とでも言いましょうか。
こんなときは、大人であれ子どもであれ「休むこと」が何よりも大事。
でも、当の本人は「学校に行けない自分はダメだ」と責めているかもしれません。
だからこそ、「今は休んでいいんだよ」「無理しなくていいんだよ」と、何度も伝えることが必要です。
休むことは、心を立て直すための大切な時間なのです。
変化の兆しを焦らず、でも観察する
心の回復は、ゆっくり時間をかけて進んでいきます。
一見、何も変わっていないようでも、実は内面では小さな変化が起きているかもしれません。
無理に話を引き出そうとせず、日常の中で子どもの様子をよく観察してみると……
表情の変化、行動の選択、小さなつぶやき—そこに、子どもなりの“変化の兆し”があるかもしれません。
言葉では表現しきれない想いを、態度や反応からくみ取っていくことが大切です。
おわりに:親子ともに“安心”から始めましょう
不登校は、子どもからの“SOSのサイン”だと思います。
まずはその声に気づき、受け止めることから始めてみてもいいのかなと思います。
私たち親にできることは、「今ここにいるあなたが大事だよ」と、言葉と態度で伝えていくこと。
少しずつの“安心”の積み重ねが、子どもの回復につながると信じています。
次回は「親自身の心構え編」として、不安や迷いとどう向き合うかについてお伝えする予定です。
どうぞお楽しみに。
※この記事が参考になった方は、ぜひSNSでシェアやコメントをしていただけるとうれしいです。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
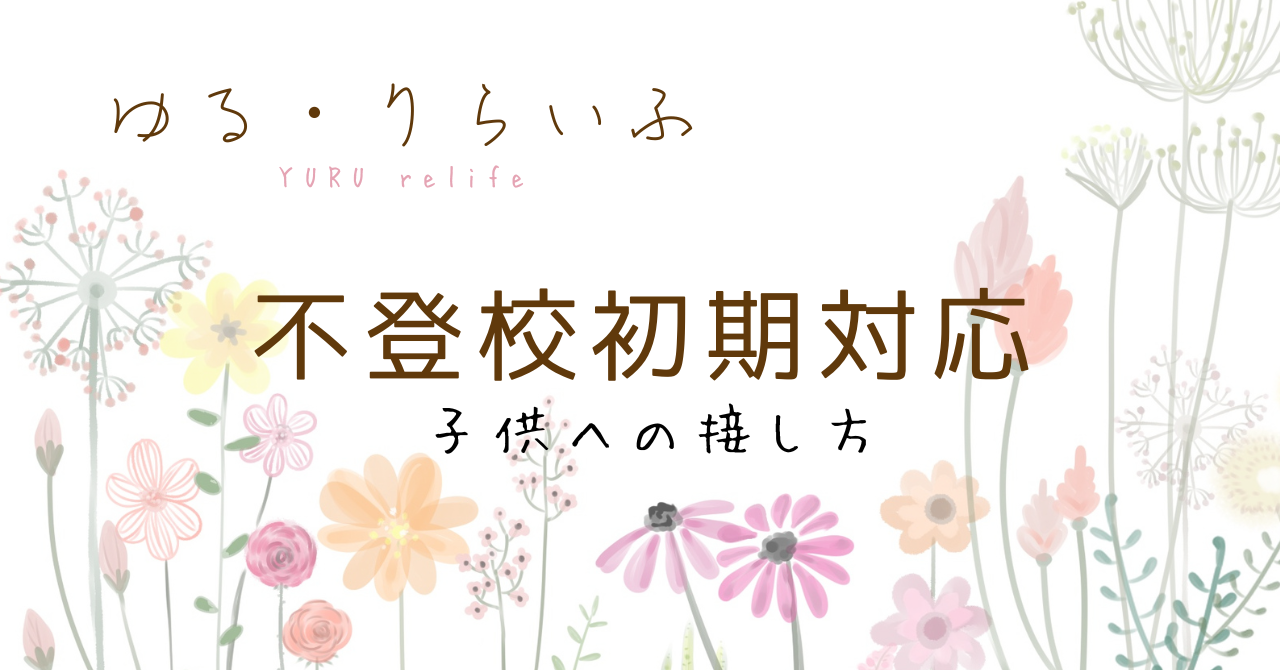
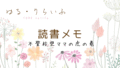
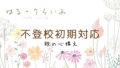
コメント