こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ 〜不登校とともに流れる、のんびり時間〜」にお越しくださり、ありがとうございます。
不登校初期の頃、子どもが家でぼんやり過ごす時間が増えて、私自身、どう接したらいいのか分からず戸惑っていました。
「学校に行けないままで、本当に大丈夫?」
「いつ回復するのかな…」
でもね、子どもにとって「学校に行けない」というのは、
「自分はみんなと違う」「ダメな人間かもしれない」
という、深くて強烈な痛みを伴う出来事なんですよね。
「楽しいことしかできない」状態になる理由
心が追い詰められると、子どもは「楽しいことしかできない状態」になります。
一見すると怠けているようにも見えるかもしれませんが、実は「つらいことにはもう心が耐えられない」ほどの限界状態。
ゲームをしていたり、動画を見ていたり、「好きなことだけに没頭しているように見える時」ほど、実はSOSを出しているサインなのかもしれません。
うちの子はそのうち、そうした“好きなこと”さえできなくなり、ただソファに横たわって、ぐったりとしたまま動けないようになりました。
見ている私も、どうしたらいいのか分からず、胸が苦しかったです。
心と体のさまざまなサインが出てきた
それ以外にも、いろいろなサインが現れました。
- 口を開けばネガティブな言葉ばかり
- ちょっとしたことで涙が出る
- ぬいぐるみを手放せなくなる
- まるで赤ちゃん返りのように、私から離れられない
- 食欲が落ちる
これは、大人でいえば「うつ」に近い状態じゃないか?
そんなふうに感じた私は、一刻も早く専門家に相談したほうがいいと、児童精神科に連絡を入れました。
児童精神科に電話した時の流れ
電話をすると、看護師さんがとても丁寧に状況を聞き取ってくれました。
「小さなクリニックのため、緊急性が高い場合には対応が難しいのですが、まずは医師が受け入れられるかどうかを判断します」と言われ、いったん電話を切りました。
翌日、「うちで診ましょう」との連絡をいただき、受診の予約を取りました。
子どもへの声かけ:「心のお医者さんに行こう」
電話をかける前、子どもにはこう伝えていました。
「心がつらいなら、心のお医者さんに診てもらおうね」
すると、意外なほどすんなり「うん」とうなずいたのです。
きっと本人も、自分が「いつもと違う」ことを感じていたのでしょう。
また、私がふだんから精神科の先生の動画や話を見ていたので、ある程度、イメージが持てていたのかもしれません。
初診の流れと診断
受診当日、まずは詳細な問診票を記入。
発達特性の有無も含めて、丁寧に確認されました。
続いて、心理士さんとの面談があり、その後、親子で診察室へ。
- はじめは親子で一緒に
- 次に、私ひとり
- 次に、子どもひとり
- 最後に再び、私ひとりで呼ばれる
という流れでした。
診断と、先生からの問いかけ
先生はこう話してくださいました。
「お子さんはASD(自閉スペクトラム症)の傾向があります。
今まで問題が起きなかったのは、環境がうまく適応していたからでしょう」
「今回の不登校はASDそのものではなく、2次障害としての反応です」
「学校という環境が合っていなかった可能性があり、今後は本人の特性に合った環境調整が大切になります」
そして先生は、こう問いかけました。
「お母さんが考える“ゴール”は、なんですか?」
私が出した答えと、先生の反応
私は少し考えてから、こう答えました。
「この子が自分らしく、前向きに生きられるようになることです。
登校できるかどうかは、ゴールではありません」
先生はうれしそうにうなずいて、こう言いました。
「でしたら、そのゴールに向かってできることを一緒に考えていきましょう」
そして、地域の福祉サービスや民間の支援など、たくさんの選択肢を提案してくださいました。
初診を経て見えたもの
この初診で、私の中で見えてきたものがありました。
- 今、我が子に何が起きているのか
- これからどうすればいいのか
霧の中にいたような感覚が、少しずつ晴れていきました。
その後、知能検査もしていただき、我が子に合ったペースで月に数回、継続して通っています。
困ったときはすぐ相談できる、対処法を一緒に考えてもらえる。
今では、先生が親子にとって一番信頼できる存在です。
受診して本当によかった
不登校の入り口に立って、どうしていいか分からなかった日々。
でも、専門家の見立てと支えがあったことで、スムーズに「次の一歩」を踏み出せました。
もし今、同じように迷っているママがいたら私は心からこう伝えたいです。
「迷っているなら、一度行ってみてください」
きっと、今より安心して過ごせるヒントが見つかると思います。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
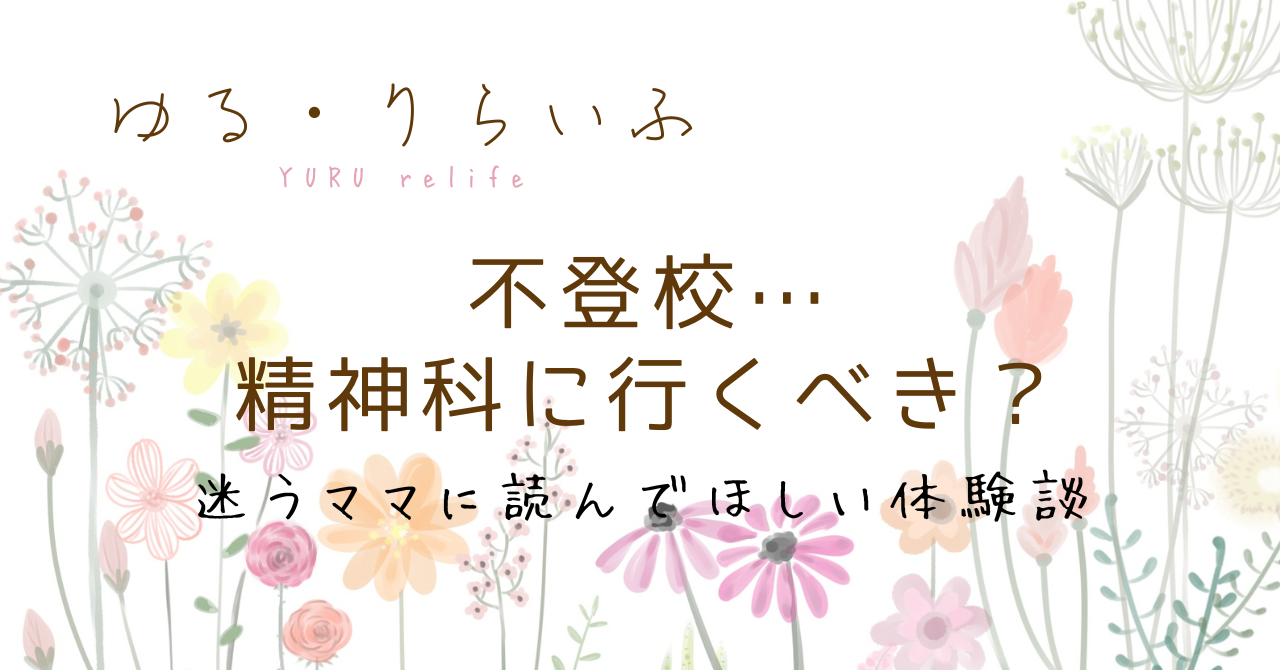
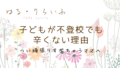
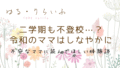
コメント