こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ 〜不登校とともに流れる、のんびり時間〜」にお越しくださり、ありがとうございます。
現在不登校のわが子ですが、小1の時にさまざまなサインを発していました。
(こちらの記事で詳しく取り上げています )
当時の私は「きっと小1の壁」「よくあることだろう」と思いつつも、どこかで違和感を感じており、「何かできることはないか」と模索していました。
その中で見つけたのが、とある民間学童です。
民間学童との出会い
小1時点のわが子は、
- たくさんの人がいると騒々しくてダメ
- 学童は特にカオスで受け付けられない
- 上の学年にいじられたりもしている様子
という状況で、私は「学校よりもまず学童をどうにかした方がいい」と考えました。
そこで、公立の学童ではなく、民間学童を検討することに。
私が重視したポイントは以下の通りです。
- 少人数のところ
- 落ち着いてアクティビティに取り組めるところ
- 宿題をちゃんと見てくれるところ
そのあたりを意識して探し、オープンしたばかりの小規模学童に決定。夏休みから利用することになりました。
民間学童で本領発揮?
こちらの学童、入会時はわが子を含めて4名しかいませんでした。
この「オープンメンバー」だったことが、わが子にとってはとても良かったようで、その後メンバーが増えても「迎える側」だったため、環境変化に適応できたように思います。
工作やお料理など、手先を動かすアクティビティが豊富な学童で、ものづくりが好きなわが子にはピッタリ。
包丁の使い方からお料理後のお片付けまで教えてもらいました。
毎週なにかしら作って帰ってきて、本当に楽しそうでした。
体を動かすアクティビティも多く、ご近所の公園でたくさん遊んだようです。
学校では「物静かな子」と言われていたわが子ですが、こちらの学童では「よく動く元気な子」。
それはきっと、本人が自分らしくイキイキと過ごせる環境だったからだと思います。
登校しぶりが落ち着く
夏休み中は公立学童と併用して週1回利用していました。
公立学童とはうって変わって楽しく通う様子から、「ここはこの子の居場所になっている」と確信。
休み明けも継続利用することに決めました。
おかげさまで、2学期からは週1回の民間学童が楽しみで、登校しぶりも少し落ち着いてきました。
その後、学校への不適応がかなり落ち着いたため、長期休みだけの利用に変更しましたが、転校するまで継続しました。
転校の際には、なにより「民間学童に行けなくなったこと」を悲しんでおり、まさに本人にとって大切な居場所だったと感じています。
今思えば、本格的に不登校になった大きな理由の一つに、「この民間学童という居場所を失ったこと」があったように思います。
第3の居場所の大切さ
“学校・家庭以外に、安心できる「もうひとつの居場所」を持つ”
これは、子どもにとって本当に重要なことなんだと痛感しています。
不登校となり、主治医からも「居場所をつくることの大切さ」を言われました。
現在はフリースクールに通っているわが子ですが、こちらもやはり彼にとって大切な居場所になりつつあるようです。
居場所としての立ち位置が強固になるほど、本人が安定していく様子が見てとれます。
子どもにとって「落ち着ける居場所」を学校・家庭以外に持つことって、本当に大事なのだなぁと、これらの経験を通して感じています。
同じような悩みを抱えるママたちへ
子どもの世界は「学校と家庭」に限定されがちですが、わが子のように「第3の居場所」を持つことで心が安定する子は、少なからずいるように思います。
母である私も、わが子が安定することで、ホッと安心することができました。
「学校に合っていない気がする…」と感じているなら、「安心できる場所探し」も始めてみてはいかがでしょうか。
きっと、その一歩が「大切な居場所」をつくるきっかけになると思っています。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
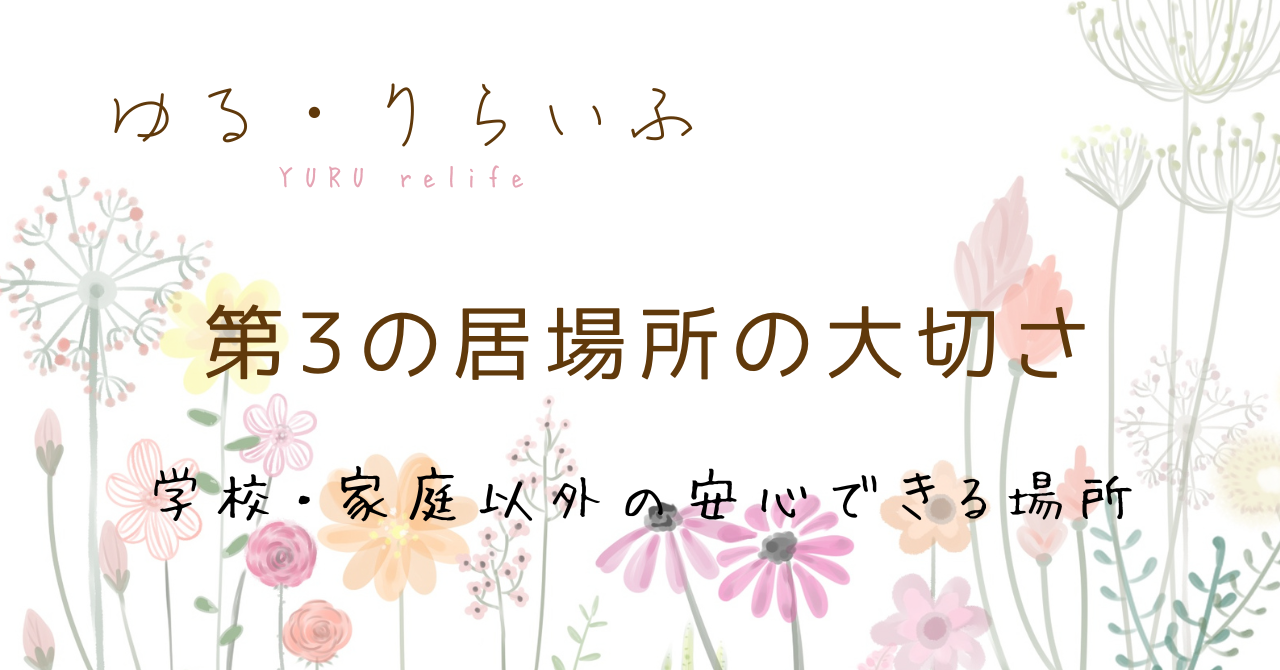
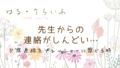
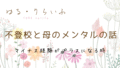
コメント