こんにちは、まいこです。
「ゆる・りらいふ ~不登校とともに流れる、のんびり時間~」にお越しくださり、ありがとうございます。
子どもが不登校になったとき、親は「どう受け止めるか」だけでなく、「まわりとどう関わっていくか」でも悩むことが多いですよね。
学校、地域、家族…
一人で抱えきれないこの状況を、少しでも軽くするために、今回は「周囲・環境への対応編」として、意識しておきたい5つの視点をご紹介します。
学校と連携することを恐れない
「学校とは関わりたくない…」
そんな気持ち、正直わかります。私もそうでした(笑)。
でも実は、先生や学校側も“どう対応すればいいのか”迷っているケースがとても多いんです。
学校には明確なマニュアルがないこともあり、先生方も試行錯誤しているのが現状とのこと。
だからこそ、対立ではなく“協力関係”として関わることが大切です。
「うちの子を一緒にサポートしてもらうには、どんな連携が取りやすいか?」と考えると、話し合いもしやすくなります。
学校を“敵”と思わず、「味方にできる存在」として、こちらから心を開いてみましょう。
我が子を心配する先生方の思いに心打たれる瞬間も、きっとやってくると思います。
早めにサポート体制を整える
不登校の対応は、家庭だけで抱えるには限界があります。
地域や行政のサポートを早めに知っておくと、安心材料がぐっと増えます。
まずは、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談してみるのがおすすめ。
地域の支援団体や制度についても教えてもらえることがあります。
情緒が不安定な場合や、子ども自身のメンタルヘルスが気になる時は、医療機関への相談も一つの選択肢。
発達特性が疑われるときも、早めに対応することで子ども自身がラクになることもあります。
「グレーゾーンだけど困っている」そんな時でも、相談を受けてくれる医療機関もあるので、遠慮せずに声をあげてみてください。
家族の足並みをそろえる
不登校への対応について、家族の中で意見がバラバラだと、子どもが混乱してしまうことがあります。
夫婦間で考え方が違ったり、祖父母が「甘やかしすぎじゃないか」と言ってきたり……
よくあることだと思います。
でも、ここで大切なのは「家庭としての一貫性」。
一度立ち止まって、家族で話し合い、方向性をそろえることを意識してみてください。
どうしても意見が合わない家族がいる場合は、一時的に距離を取るのも選択肢。
今は“親子の心を守ること”がいちばん大切です。
子どもの同意と安心感を大切にする
支援機関と話す、学校と連絡を取る——
どれも親として必要な行動ではありますが、
子ども本人の気持ちを置き去りにしないことがとても大切です。
「知らないうちに勝手に話が進んでた」
これ、子どもにとってはすごくショックな出来事なんですよね。
できる範囲で、「今こんなことを考えているよ」「こういう人に相談してみようと思ってるよ」と、子どもに説明し、納得を得るよう心がけてみてください。
それだけで、子どもの安心感は大きく変わるはずです。
“環境そのもの”を整えていく視点も大切に
不登校の背景には、子どもにとっての「環境のストレス」がある場合も少なくありません。
家庭、学校、社会——さまざまな場面でのプレッシャーが重なって、心が折れてしまうことも。
今は、「学校に戻す」ことよりも、子どもが安心できる環境を整えることが最優先です。
- フリースクールの見学
- オンライン学習の活用
- 家庭内のルールの見直し
- 子どもが「ホッとできる場所」づくり
こうした環境調整を、焦らず、ゆっくり取り組んでいくことが、回復への近道になります。
おわりに:ひとりじゃない。つながりが安心感を育ててくれる
不登校の対応は、子どもと親だけで乗り越えようとすると、とても苦しくなります。
でも、少しずつ周囲と関わっていくことで、心がラクになる瞬間もきっとあるはず。
学校とも、支援機関とも、家族とも、 “子どものための専属チーム”として、協力できる関係が作れるといいですよね。
そして何よりも大切なのは——
子ども自身が「自分は大事にされている」と感じられること。
それを軸に、できることを一つひとつ、進めていきましょう。
【シリーズ振り返り】不登校初期対応の3本柱
- 子どもへの対応編|登校刺激を避けて「安心の土台」をつくる
- 親自身の心構え編|まず親が落ち着くための5つの視点
- 周囲・環境への対応編(今回)
どれかひとつでも「そうかも」と思えたら、
ぜひ周囲にもシェアしていただけたらうれしいです。
このブログでは、小学生の息子とともに過ごす不登校の日々の中で感じたこと、調べてわかった情報、そして母親としての戸惑いや気づきを、同じように悩むママたちへ向けてゆるっと綴っています。
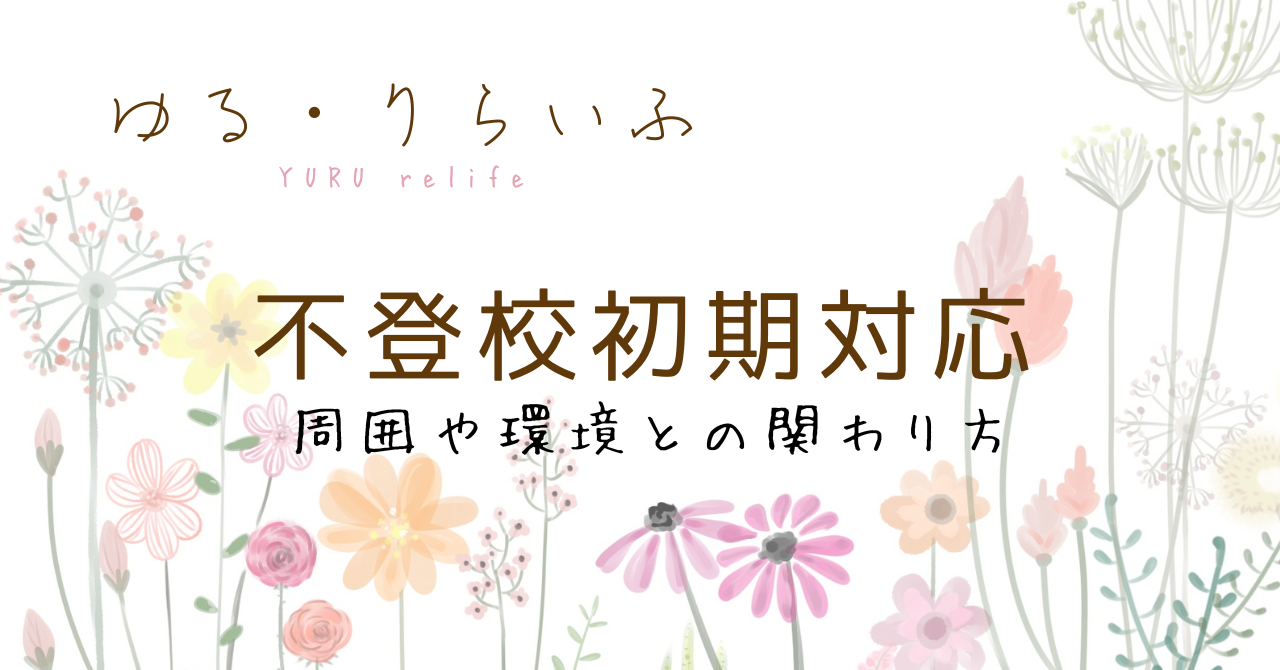
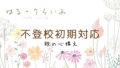
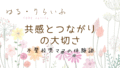
コメント